\元PTA会長の経験談が改革策のヒントに/
前ページでの内容を踏まえ、幼稚園や小学校、さらには高校でもPTA会長や役員を長く務めたことのある木下尚昭氏に、会長になられた経緯や大変だったこと、更には、やりがいや、保護者やPTA会員の方々にアドバイスしたいこと等をインタビュー形式で語ってもらった。
長女が函館市内のK幼稚園に在園していた時、10数名の有志がお金を出し合い親父の会を創立。私も園児のためにと、お遊戯室のワックスがけや遊具のペンキ塗り等の活動に積極的に参加していたことがきっかけで、次女が入園した時に前任のPTA役員さんから声がかかって会長を引き受けることになった。以後、3年務めることになった。
幼稚園や園児のために、これまで続いてきたPTAを引き継ぐとともに、PTA活動の見える化を図るために、変革に関わっていいかなければならないと思った。そして、さっそく取り組んだことは、園の事務担当の先生の協力も得て、PTA関係の書類を整理し会員の方々にPTAの組織や活動内容、会費の収支決算等を理解してもらうようにした。
運動会や卒園式等の行事で「PTA会長挨拶」をするために、原稿の準備と暗記するために前日から何度も練習したことが大変負担だった。でも、2年目からはその負担も軽くなってきた。会長をやって良かったことは、先生方の大々的な協力を得ながら各種PTA行事やお父さんの会の活動が、回を増すごとに盛況になっていった。活動を共にした当時のPTA役員やお父さんの会のメンバー、先生方とは今でも繋がりが持てている。
娘のためにと、在学している学校の行事やバザーなどのPTA行事に頻繁に参加していると、学校の方から自然と声がかかってきて、つい引き受けることになった。これも、幼稚園で会長をやり遂げれたという自負心があったからなのか。高校のPTA会長の時は、町内会の役員もしていたし、会社の仕事もシステム変更等で忙しかった。また、高校の時はコロナ禍で学校行事も制限されていたので伝統の「行燈づくり」のノウハウが継承できないのではというピンチに遭遇。そこで、経験者を集め、詳しい方の作業場所(木古内)まで出向き、作業行程とノウハウをビデオに撮影し、それをYouTubeで配信することでピンチを脱した。
会費+αを学校に収めるだけの組織ではいけない、子どもの教育のために、それが適切に執行されているか親としてチェックすることや学校に意見を述べていくような存在でなくてはならない。高校では、PTA会費のほかに部活補助費等を徴収する、金額もかなり高くになるので、その使途を保護者にしっかり知らせなければならない。
たった数年間だけなので、実績が残せたときは達成感がある。高校のPTA会長の挨拶で会員の人たちに話したことは「子どもと一緒に高校生活3年間を楽しみましょう。行燈を作るときは大変だったけど終わってみると楽しかったね!」と。
振り返ってみて、一番濃かったのは幼稚園の時。役員会は、平日の午前中にやっていたので会議に参加するために午前中年休をとって、昼食を摂る間もなく午後から出勤した。また、役員会の資料を作るために前日遅くまで準備した。資料をちゃんと作ったのは情報共有が大事なので。このことは現在役員をやっている町会でも言えることで、情報を出席できなかった人たちのために、ネットにつなげることができる環境であれば、ズームを使いオンラインで会議に参加できるので時間的な負荷がかからないし家にいてもできる。高校のPTA会長の時、ズームで会議する方法を伝授してPTA会議をやった。コロナ禍の時、授業をリモートでやっていた先生もいたけど、得意でない先生はやれていなかった。学校運営協議会の時、学校側にどの先生もリモートで授業ができるように学校で研修をしているのか質問したことがあり、その必要性を提言した。高校でPTAの会長職を退いた後も、PTAの引継ぎを含めて1・2年学校運営協議会に所属してアドバイスした。学校の教育改善に向けて意見したこともある。その協議会が有効に機能するためにも。
子どもの就学や就園を通して交流を持てた保護者同士のつながりは宝物。保護者とのつながりができるとPTA活動の楽しみが湧いてくる。せっかく関わったのだから、楽しまなくては。自分が困っているときにはそういう仲間の存在が助けになるし、相手が困っているときは手を差し伸べてあげたい。私は実は人見知りだったけど、それを乗り越えるためにも役員を引き受けてた。また、乗り越えることによってたくさんの人たちとのつながりが持てるようになってきた。それが自分の財産になっている。
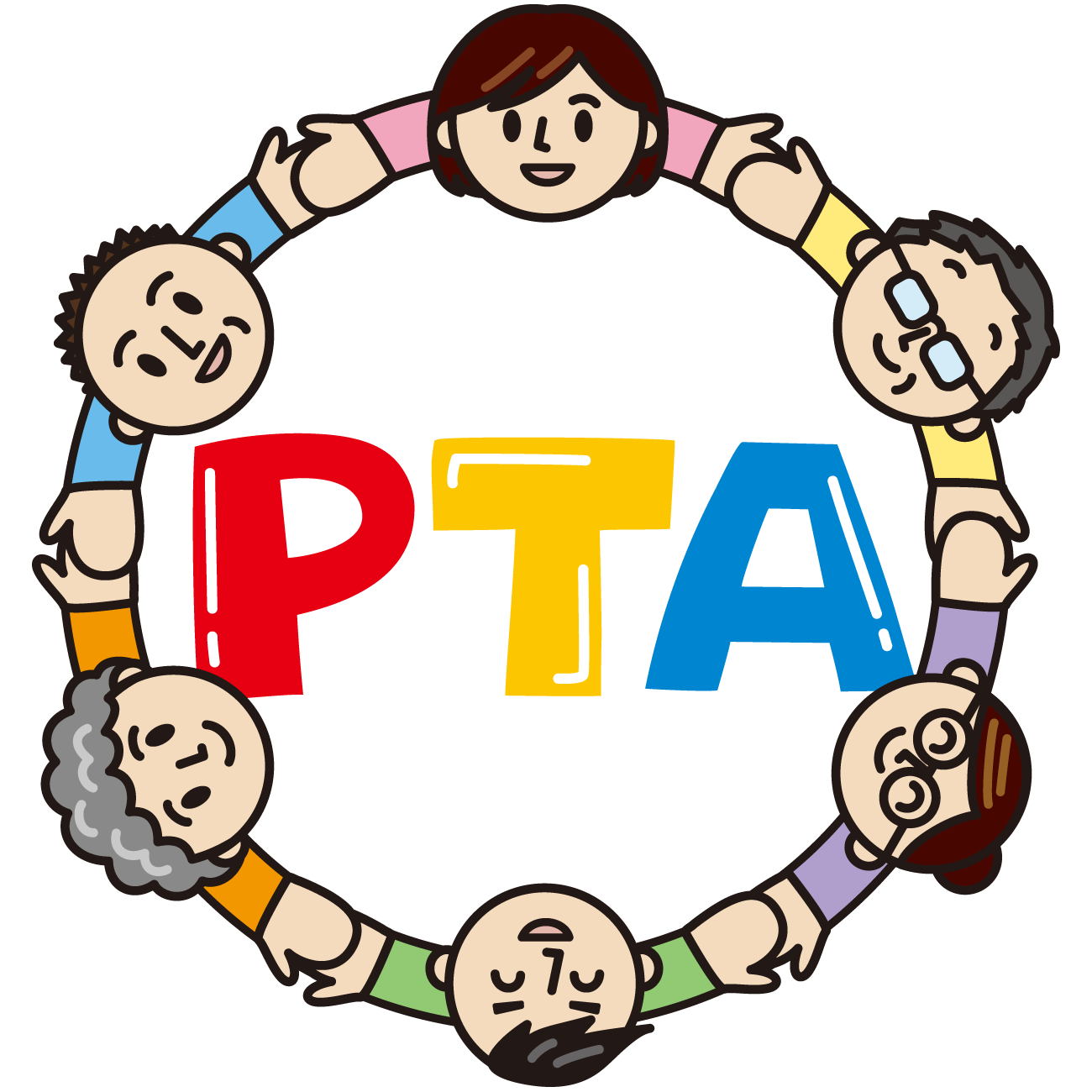
できない理由を並べ立てるより、やる方法を考える。やれるときにやっておく、やりたいと思ってもできない時期が来るので、どうせなら。
インタビューに協力いただいた木下さん
ありがとうございました!
PTA活動には、賛否両論がつきもの。PTA活動による保護者や先生方の負担は、現代ならではの課題と言えるでしょう。しかし、PTAがあることで他校や地域との連携がスムーズにできるなど、メリットも多くあります。そもそもPTA活動は、子どもたちが健全に育つようにと組織化されたもの。いつの時代も子どもを想う気持ちは同じはず。子どもたちの健やかな育成を願い、望ましい環境を提供できるよう、地域や時代に合わせたPTA活動を模索し、実践していけるといいですね。木下氏のようなPTA会長が、今求められています。
次回のあつまさ先生の道しるべは11月頃を予定しています。
少しお休み期間に入りますので、次回更新をお楽しみに♪



